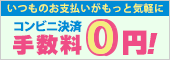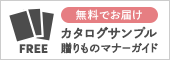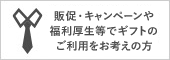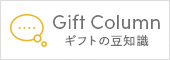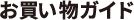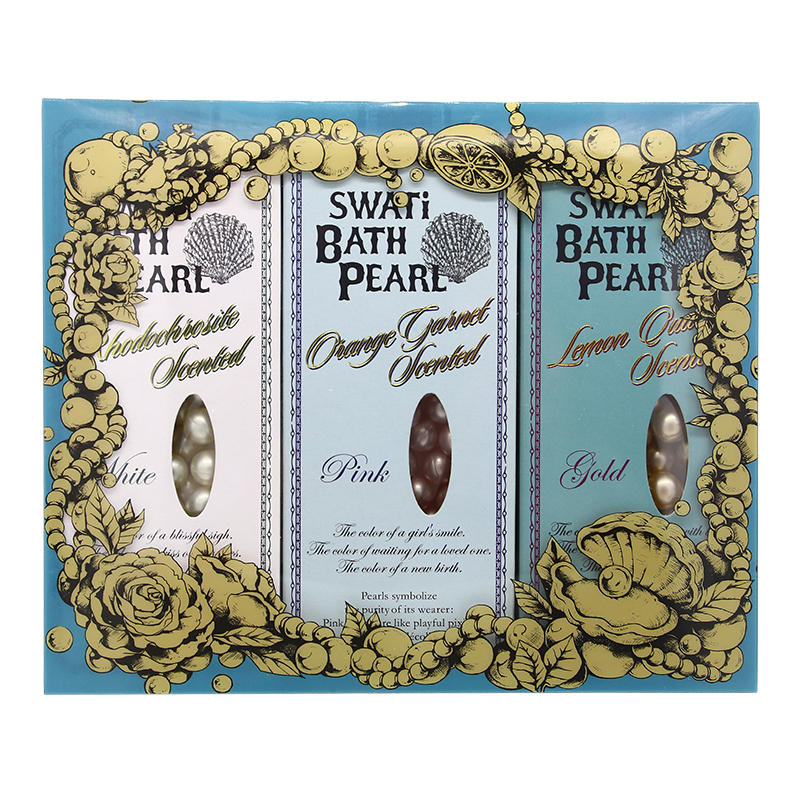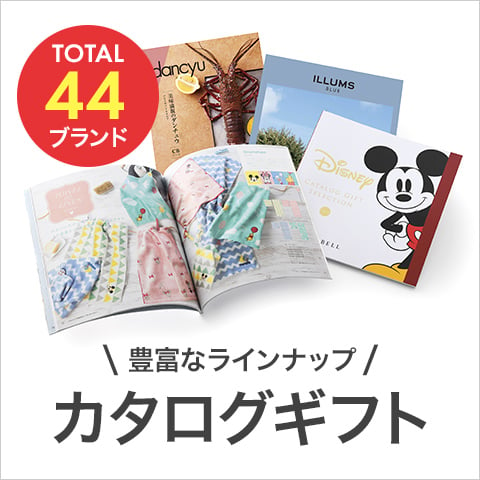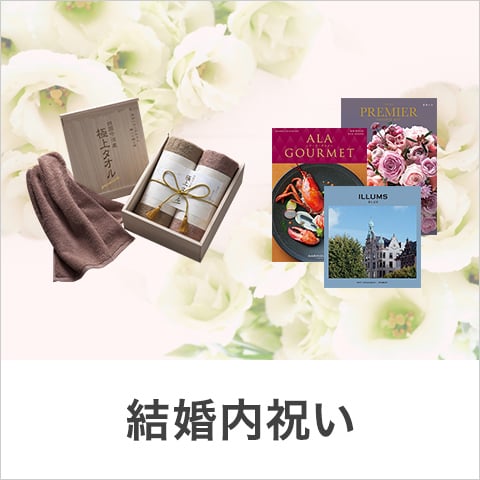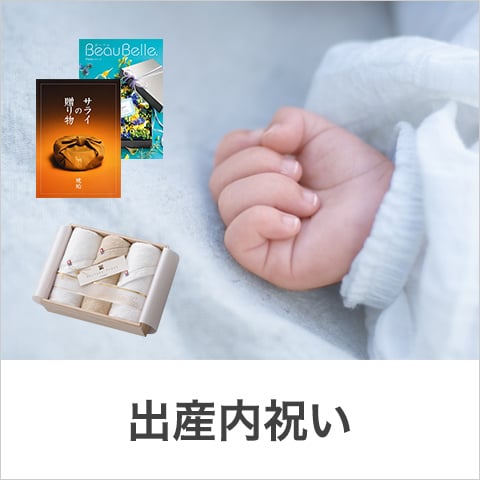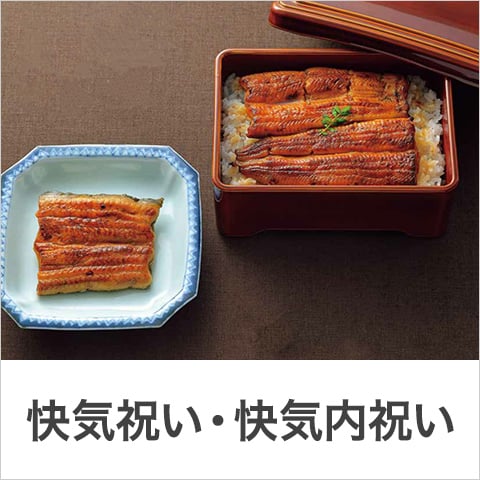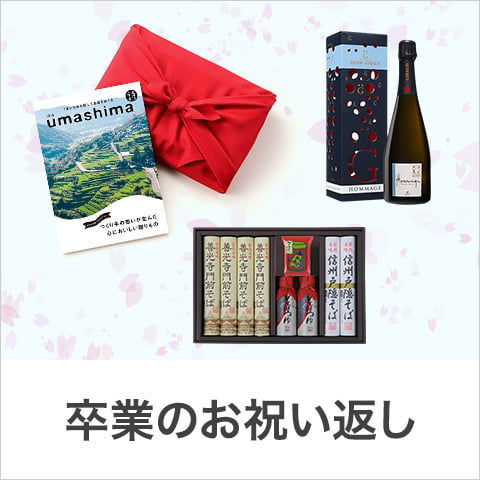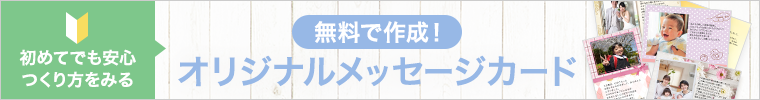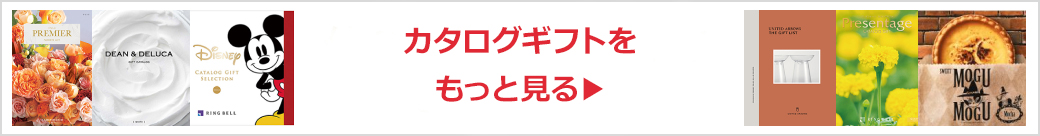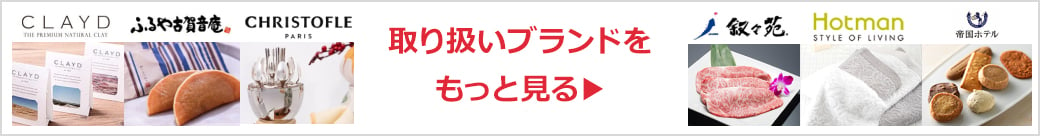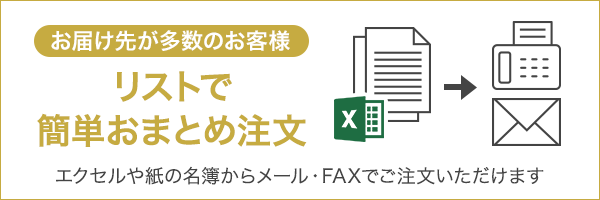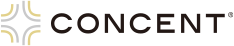|
注目のキーワード
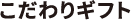
お返しを贈る
お祝いを贈る
その他のギフト
価格で選ぶ

|
【二十四節気】雨水(うすい)って何?雨水にひな人形を飾ると良い理由は? |
|
|
|
|
お客様の個人情報は、プライバシー保護のためSSL暗号化通信で送信しています。
© CONCENT Corporation all rights reserved.





























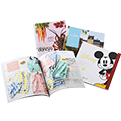

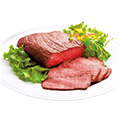




























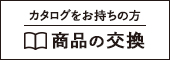

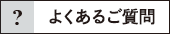
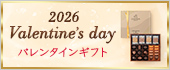
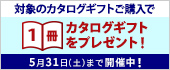
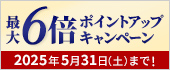

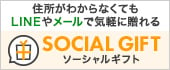

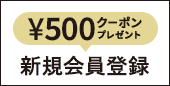
 法人ビジネスギフト
法人ビジネスギフト